SSH
日 時: 令和3年10月6日(水) 6、7校時
場 所: 本校講義室1
対象生徒: 高校1年生 SSコース選択者
高校1年生SSコース選択者を対象に、「落下モデルコンテスト」を10/27(水)に行います。コンテストは、折り紙1枚とクリップ1個で作成した落下物の滞空時間と飛行距離を測定して競います。今回はコンテストに向けて仮説を立て、規定ルール内で滞空時間と飛行距離が長いものにするための発想力と独創性のある機体を作成し、実際に落下させて確認しました。
今回の結果を活かし、次回はコンテストに向けた情報取集や機体の作成に取り掛かります。生徒の皆さんは優勝を目指して頑張ってください。




SSH
日 時:令和3年9月22日(水)5・6校時
場 所:大講義室、各教室
対象生徒:高校1年生 GSコース選択者
高校1年生GSコース選択者を対象に、「地域探究」を実施しました。今回は、凸版印刷様より、稲田優史氏、川口一八氏、佐藤伸一氏の三氏を講師に迎え、「Society5.0とデータ分析」をテーマに講義をしていただきました。
「Society5.0が目指す未来像」、「Society5.0で求められる力」、そして「データ分析の流れ」について、身近な例を交えながら詳しく教えていただきました。様々な情報があふれる社会の中で、必要な情報を選択、整理し、その中から価値を見出すデータ分析の能力は、Society5.0で重要な力になることを、実感した生徒も多かったようです。
続いて6校時は前時の講義を踏まえ、RESAS(地域経済分析システム)を活用し、各地域の人口構成比や昼夜間人口比率を調べました。今後もデータ分析のノウハウを活かしながら、探究活動に取り組んでまいります。
※この活動は9月23日(木)の福島民友新聞にも掲載されました。


SSH
日 時:令和3年9月30日(木)
場 所:大講義室
対象生徒:高校1年生 SSコース選択者、高校2年生 希望者
1年生のSSコース選択者および2年生の希望者を対象に、医療に関する講義を行いました。
前半では福島県立医科大学附属病院の引地先生にご来校いただき、本物の内視鏡や、実際の現場で撮影された動画を用いて講義をしていただきました。希望者の中から選ばれた生徒は実際に内視鏡に触れて操作することもでき、記憶に残る経験になったと思います。
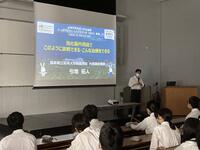



後半は、オンラインで会津医療センターの山中先生に地域医療に関する講義をしていただき、問診時に気を付けていることや、奥会津にスポットを当て、地域に密着した医療がどのように行われているのかなどをお話いただきました。問診時に重要な傾聴・共感などは日常生活における人間関係にも役立つことであり、すべての生徒にとって学びのある時間になったことと思います。



お二人の先生の講義を通し、生徒たちは自分の将来や医療現場に対する見識を広げる機会となったのではないでしょうか。
SSH
日 時:令和3年9月15日(水)
場 所:本校大講義室、教室
対象生徒:高校1年生 GSコース選択者
高校1学年GS(グローカル探求)コースでは、9月より「地域探究」が始まりました。今回のテーマは「会津・地方創生プロジェクト」です。5~6月に実施した「探究入門」での経験を生かし、会津各地域の課題を見つけ、解決に向けた活動を行います。実現可能性の高いプランの構築に向けて地域と協働して取り組み、最終的に、生徒たちが考えたプランを地方自治体や企業の方へ提案します。
今回は、全体講義で「地域探究」の活動で実施していく内容について説明を受けた後に、各チームに分かれてブレーンストーミングを行いました。生徒たちは自分たちが選んだ地域の魅力や課題について、様々な角度から意見を挙げていました。この「地域探究」を通して会津の魅力を再発見し、そして会津の各地域が抱える課題に対して自分事として捉えて考えていく時間にしてほしいと思います。


SSH
日 時: 令和3年9月27日(月) 14:00~15:30
場 所: 本校大会議室
対 象: 本校教員 10名
アース製薬と福島県との連携の一環として、教員を対象としたアース製薬様の生物飼育室のオンライン見学に参加しました。
100種類を超える害虫を100万匹以上飼育している虫の飼育室や効力試験についてオンラインで見学をさせていただきました。ゴキブリの生態や貴重なゴキブリの脱皮の様子など興味深いものでした。この他にも様々な害虫の飼育や殺虫剤の効果などについて講義していただきました。この研修を通して、今後生徒たちに課題研究のテーマ設定の時などに役立てていきたいです。
お忙しい中ありがとうございました。


SSH
日 時:令和3年9月22日(水)
場 所:本校各教室
対象生徒:高校1年生 SSコース選択者
高校1年生SSコースの生徒による、ブナ林研修の発表会が行われました。
夏季休業中に実施した「SSH野外研修」で行った調査を通して、班ごとに研究・考察を行い、ブナ林に対する理解を深め、その内容をポスターにまとめて発表を行いました。
生徒たちは担当教員による指導のもとポスターの作成と練習を行い、本番に臨みました。とても緊張した様子でしたが、どの班も熱心に発表を行っていました。
後日、教員による審査と生徒による投票により順位を決め、表彰を行う予定です。
生徒の皆さん、お疲れ様でした。
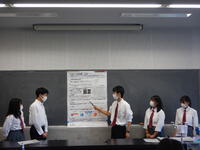
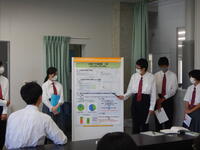
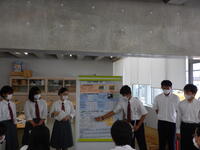
SSH
日 時: 令和3年9月10日(木) 15:20~17:45
場 所: 講義室1、高校特別教室1、理科実験室1、第1理科室
対象生徒: 高校2年生SSコース選択者 40名
東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故後における、福島県の現状を伝えるために、生徒自身で正確な知識を発信できる力を育成する目的で実施したプログラムです。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)さんの御協力のもと、オンラインで実施しました。
初めに、事前レクチャーの映像を見た後、「福島第一原子力発電所の廃炉に係る現状と今後の課題」としてNDFの福田俊彦さんから講義を受けました。15の疑問や不安なことについて、丁寧に解説していただきました。
その後、8班にわかれ、「問いをたてる」という内容でグループワークを行いました。10分程度で各班で疑問点などに対して問いを立て、その問いに対しNDFの福田さんから1時間程度回答してもらいました。
<主な質問内容>
- 燃料デブリを取り出した後どうするのか
- 処理水、とくにトリチウムについての取り扱いについて
- 廃炉に関わっている人や作業員について
●生徒の感想(一部)
- 廃炉には様々な問題があるが、今回のようにその取り組みを理解することによって自分たち自身で問題点や解決策を考えることも可能になると思った。今回、疑問を出し合って考えを深めることができたのはとても良い経験だったと思う。今まで廃炉の危険性を不安に思っていたが、この研修で詳しく説明を受けたため私たち若者がいつまで続くか先の見えない廃炉の問題の次世代の担い手として尽力していくべきだと改めて思った。今後このような話題も積極的に取り入れて、さらに考えを深めていけたらと思う。



SSH
日 時: 令和3年9月9日(木) 放課後
場 所: 本校 理科実験室1
対象生徒: 高校1年SSH探求部 7名 高校2年SSコース選択者 3名
前回(※7月2日:(2)硫酸ナトリウム処理)までに薬品処理をすべて終了し、これからサンプルから浮遊性有孔虫の化石拾いに入ります。今回は、県立博物館の相田優さん、猪瀬弘瑛さん、吉田純輝さんをお招きして化石拾いの指導していただき、実践まで行いました。
双眼実体顕微鏡を用いて1mmにも満たない化石の見つけ方、取り出し方、保存の仕方を学びました。生徒たちは、初めて見る有孔虫化石に戸惑いながらもじっくり観察し、見つけだした時は喜びの表情を浮かべていました。これから1サンプルにつき約200個体を見つけ出します。頑張っていきましょう!




SSH
日 時: 令和3年8月6日(金) 9:30~12:00 13:00~15:30
場 所: 本校 理科実験室
対象生徒: 小学生5、6年生対象 205名
主に会津地区の小学校5、6年生、約200名が参加し、午前の部と午後の部に分かれ、それぞれ物理、化学、生物、地学、情報の5つの講座を行いました。
今回も会津学鳳中学校情報科学部の生徒達がTA(ティーチング・アシスタント)として、活躍してくれました。実験中、小学生へ丁寧に対応をしてくれて実験がスムーズに行えました。
マスクの着用、3密を避ける、換気を十分にするなど、新型コロナ感染症対策を十分に行い実施しました。
それぞれの講座の内容は次のとおりです。
- 分光器をつくろう~いろいろな光をかんさつしてみよう~(物理)
分光器を組み立て、それを使って光を観察しました。

- レモンの不思議実験! (化学)
レモンをテーマに様々な実験を行いました。レモンに含まれる成分は、リサイクルや、食品保存の分野で大活躍しています。楽しくて役に立つ実験を行いました。

- 身近な野菜でおもしろ実験 (生物)
身近にあるタマネギやニンジン、パプリカなどの野菜を使って実験をしました。野菜で染色、野菜ロケット、野菜や果物の中のビタミンCの量を測るなど、いろいろな実験を行いました。

- 雲のメカニズム実験!
簡単な実験を通して水の変化や気圧と温度の関係を確かめ、ペットボトルを使って雲の発生する様子を観察しました。また、過冷却の実験も行いました。

- ロボットを組み立てて動かしてみよう! (情報)
LEGOブロックを使って組み立てた二輪駆動型ロボットを、プログラミングして動かしました。

各講座とも楽しんで実験をおこなうことができました。これをきっかけに科学への興味・関心を深めてもらえると幸いです。